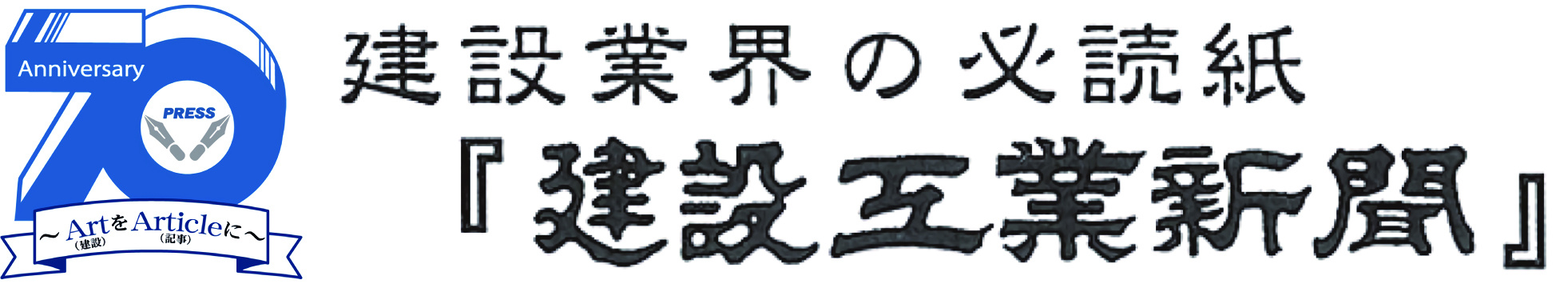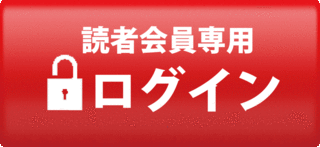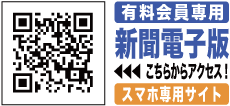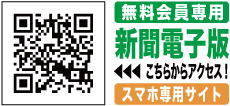コラム
みちしるべ
2024-06-07
近年、国際市場で和牛の活躍が目覚ましい。輸出額の伸びも好調で、国は10年間で6倍の出荷目標を掲げている▼肉といえば赤身の諸外国から見て、サシの入った霜降りの和牛は唯一無二の味わいを持つ特異な品種。ただ、肥育に使う飼料はほぼ輸入に頼っているとか▼人口増加が続く途上国の台頭で飼料需要は右肩上がり。厳しい円安局面で強い通貨に「買い負ける」ことも起きている。マクロな食肉の需給バランスが崩れる「タンパク質危機」の脅威は、思ったより身近に迫っているのかもしれない▼建設業界を襲ったウッドショックもまた、これとよく似た構図と言える。しかしプラントベースフードや培養肉のような代替手段が未だ見えてこない中、国内自給率を高めるための議論はおろそかにできない。(鵯)
みちしるべ
2024-06-06
先日、街なかで珍しい昆虫を見かけた。体長は小さく、黒色で一瞬身構えたが、よく見ると光っている。蛍だったのだ。住宅街だったので大変驚いた▼幼いころは自宅近くにある樗谿(おうちだに)公園に、家族と一緒に蛍を見に行っていた。しかし、環境の変化などで年々蛍が減っていき、蛍を見に行くこともなくなった▼街なかでは宅地開発が進み、住宅などが建てられている。十数年前は田んぼや畑があった鳥取市の中心部に近い地域も、今では真新しい住宅やアパートなどが建ち並ぶ▼都会に行くと迫りくるビル群に息が切れてしまう。鳥取のような地方でもそこら中に建物が建ってしまうと、自然が多いというせっかくの地方の良さが失われてしまう。地方の良さを取り入れた街づくりを県内自治体に期待する。(隼)
みちしるべ
2024-06-05
電気料金の値上げが止まらない。6月使用分の電気料金は電力会社10社全てで値上がりに。3カ月連続で上がっているが、これから暑くなる季節。冷房の使用で家計は圧迫されるだろう▼日本の国内発電電力の割合は、化石燃料を使う火力発電が7割近く占める。天然ガス・石油・石炭などの燃料価格が高騰する限り電気の値上げは止まらない。電力会社は更なる単価・プランの見直しが必要だろう▼電気料金は上がっているものの、やはり家電は生活する上では欠かせない。東日本、西日本では電源周波数が違うことにより、東日本で購入した家電を西日本で使用、またその逆をすると、性能の低下や故障を招く原因に。引っ越しをするとき注意が必要となる▼それにしても電気料金はどこまで上がるか。解決策はあるだろうか。(鴎)
みちしるべ
2024-06-03
「日が長くなっても、早く現場を切り上げなければ」―時間外労働の上限規制がはじまった。とは言うものの、「時短」に苦しんでいる建設会社は本当に多い。週休2日を見込んだ標準工期が適切なものになっているかどうか▼会社または自宅から現場まで、移動する時間もあって実際に現場を叩ける時間は限られる。遠い現場であれば、会社に戻って書類作りの時間もなかなか取ることができない。また、工期が長い現場ともなれば、冬を迎える前になるべく進捗を上げておかないと、と考えるのはごく自然だろう▼机上の空論。そもそも時短とセットで従来の仕事量をこなすには、業務効率のアップと人員増が伴う。そこが欠けたまま、現場は生産性の向上どころか、まったく逆の方向に進んでいる。働き方改革は進んでいますか。(鷲)
みちしるべ
2024-05-31
旅行中などで渋滞にはまった時に、「どこでもドアがあれば」「車が空を飛べたら」など、なんとか移動時間を削減できないものかと考えてしまうことがある▼先日、アメリカのベンチャー企業が日本航空と提携し、空飛ぶタクシーの試験飛行に成功した。将来はパイロットがいない自動飛行を実現し、日本での事業展開も目指しているという。また、2025年の大阪・関西万博では、空飛ぶクルマが人を乗せて大阪の空を飛ぶことが決まっている。どちらも楽しみなプロジェクトで、着実に夢の実現に近づいている▼4月から時間外労働の上限規制が開始したが、対応に苦慮している印象だ。移動時間の短縮はこの問題にも良い影響を及ぼすだろう。いつかは重機たちが空を飛ぶ時代がくるかもしれない。(雛)
みちしるべ
2024-05-30
キャベツなどの値段が高騰している。一般の人は値段が落ち着くまで我慢もできるが、食を提供する地元の店舗にとっては値上げも難しい。深刻だ▼農家はもっと大変だろう。長い時間をかけて生産の基盤を作るが、栽培には天候が大きく左右する。それでも、農作物を育て上げて出荷にこぎつける人達は、食料の自給率が極めて低い日本を支える▼建設業界で働く人も同じだ。一人前になるには長い時間がかかる。完成までの工程を描く調査や施工業者の技術者。そして、多くの職人技で現場を仕上げて行く姿が頼もしい▼業界団体の定時総会では担い手の確保、人材育成という言葉がトップにくる。高齢化は進むが、若い人も多く働いている。育つには手間もかかるが、伸びる姿を見るのも楽しみの一つ。(鷺)
みちしるべ
2024-05-29
中年男性、30代の男性と女性の3人のうち、役職が最も上なのは、どの人だろうか。ある連続ドラマで、取引先から一緒に訪れた3人に対し、応対者が中年男性を上司と思い込んで話を進め、場がおかしくなるシーンがあった▼役職者は実は女性。昨今は女性活躍、中高年の役職定年に伴い、立場が多様化。年齢、男女問わず実力ある人材が登用されることも珍しくない。ちなみにドラマでは「可愛い花屋がある」と聞きつけた主人公が、どんな女性が店員かと興味津々に訪れると、男性だったという場面も。先入観は恐ろしい▼業界では新年度の工事が続々と発注されている。忙しくなり始めたが、工程管理や営業活動で思い込みはないか。発注側も前例踏襲ではなく、柔軟な対応に向け、時には立ち止まって考えてみるのもいい。(鴛)
みちしるべ
2024-05-28
各所で6月議会の日程が固まり、補正予算の動向も見え隠れ。まずは分かりやすく土木費の区分に目を通すが、教育費や観光振興費などにも意外な大物が潜んでいるから油断は禁物だ▼予算書に綴じられた数字の羅列に価値の大小を見出すのも、「心の会計」と言われる心理現象の一種かもしれない。我々は取得方法や用途によって、無意識にお金に感じる重みを変えている▼例えば労働の対価として得た1万円と、たまたまギャンブルで勝った1万円。後者はあぶく銭と見て「パッと使ってしまおう」と考える人も多いのではないか▼では、不正な経路を辿ったお金はどんな心の勘定科目に入るのか―数字の多寡では推し量れない問いを挟んで、政治資金規正法改正を巡る与野党の舌戦は長期戦の様相を呈している。(鵯)
みちしるべ
2024-05-27
流行はリバイバルする周期が20年とも言われている。音楽は、10代中心にSNSを通じて平成前半の曲が流行っているし、ファッションも「シャツイン」スタイルは、バブル期を彷彿とさせる▼ほかにもかつての一発屋芸人が再びテレビに出ていることも。恐らく、当時子どもだった番組スタッフや共演者が、もう一度見たいといった理由でブッキングしているのだろう▼戸建て住宅でもある意味「リバイバル」と言えるのか。平屋建てを建てるケースが増えつつあるそうだ。メリットとして、コスト面で得だったり、地震で倒壊しにくい、少人数向き、ということが挙げられる▼県内の戸建て住宅着工数は、年々減少傾向。かつての流行を取り入れた住宅というのも一つ、着工数増加のアプローチになるか。(隼)
みちしるべ
2024-05-24
今日24日はゴルフ場記念日。1903年にイギリス人が神戸ゴルフ俱楽部をオープンし、日本初のゴルフ場が完成したことで制定された▼ゴルフ場を手掛けたイギリス貿易商アーサー・ヘスケス・グルームは、六甲山に魅了され思い付きでコースの建設に着手。除草、伐木や造成など仲間と共に手作業で行い、オープン当時は4ホール。完成までに3年かかったという。奇想天外な発想から行動力は、日本ゴルフの始まりと言っても過言ではない▼日本のゴルフ場は2000コース以上、中でも名門コースを手掛けた「東(柔)の井上誠一、西(剛)の上田治」は日本のゴルフコース設計の二大巨頭である。自然を活かした作り、土砂を盛り高低差を付けた作り。それぞれ違う特徴であり、読者が好むのはどちらだろうか。(鴎)